皆さん、こんにちは。ブログ「パパシードの子育て奮闘記」へようこそ。運営者のシードと申します。現在は生後89日の娘と妻との3人暮らしです。
本日をもって、私の育児休業が終了します。明日からは、再び会社員としての日々が始まります。それに伴い、来週からは妻と娘が里帰りすることになりました。このブログでは、育休最終日である今日を振り返りながら、育児の喜びや苦労、そしてこれから始まる新しい生活への思いを、私の率直な言葉で綴っていきたいと思います。
育休最終日の朝、そして予期せぬオフの日
今朝はいつもより少し早起きでした。午前6時、ベビーベッドの上で娘が元気よくバタバタと足を動かしていました。まるで歩く練習でもしているかのようです。その愛らしい姿を見て、私と妻は自然と目が覚めました。生後89日、つまり2ヶ月半を過ぎたばかりの娘ですが、日々驚くようなスピードで成長しています。首がすわりかけ、自分の手を見つめたり、声を出すようになったり、笑顔を見せてくれる時間も増えました。生まれたばかりの頃は、ただ泣くことしかできなかった小さな命が、今では私たちにたくさんの喜びと感動を与えてくれる存在になりました。
育休中、私は主に娘のおむつ替えと寝かしつけ、そして妻の食事の準備を担当していました。朝食後、近所の体育館で社会人サークルがバスケをしていると聞いていたので、参加してみようかと妻に話しました。体を動かすことでリフレッシュできるのではないかと思ったのです。しかし、念のため参加人数を確認したところ、なんとたったの2人。試合形式でバスケをすることは難しそうだったので、今回は見送ることにしました。
土曜日の朝、バスケサークルに参加する人が少ないのは少し意外でした。もしかしたら、皆さん家族との時間を大切にしているのかもしれませんね。この件について調べてみたところ、社会人スポーツサークルへの参加は、平日の夜や週末の午後に集中する傾向があるようです。特に子育て世代は、土曜日の午前中は家族サービスや子どもの習い事などで忙しいことが多く、参加者が少なくなる傾向にあるようです。
里帰りへの出発と、小さなトラブル解決
午前中に家事を済ませ、午後からは妻の実家への里帰りに出発です。今回の運転手は妻。約2時間のドライブです。妻は車線変更が苦手だと常々言っていますが、地元の道を熟知しているため、スムーズに運転していました。右折専用レーンをしっかりと避けて運転しているあたりは、さすがとしか言いようがありません。
妻の実家に到着後、まずは娘の様子を確認できるベビーモニター「CuboAi」を組み立て、通信設定を行いました。CuboAiは、AI技術を搭載した高性能なベビーモニターで、赤ちゃんの寝返りや顔が覆われていることを検知して知らせてくれる機能があります。これがあれば、離れた場所にいても娘の安全を確保できます。
次に、私の車から義母の車へチャイルドシートを付け替えました。この作業で、まさかのトラブルが発生したのです。
私が使っているチャイルドシートは、ISOFIXという規格に準拠しています。ISOFIXとは、シートベルトを使わずにチャイルドシートを車に取り付けるための国際標準規格で、正しい取り付けを簡単に、より確実に行うことができるのが特徴です。日本では2012年7月以降に製造された車にはISOFIX対応の金具の取り付けが義務化されています。義母の車もその義務化以降の車だったので、スムーズに取り付けられるはずでした。しかし、車内の取り付け金具がどこにも見当たらないのです。
金具を探してはシートの隙間をのぞき込み、四苦八苦しました。もしかして、金具がついていないのでは? 車屋さんに行って金具を購入しないといけないのか? そんな考えが頭をよぎり、一人で迷走してしまいました。
結局、金具はシートの下の方に深く埋もれていたというオチでした。シートの奥まで手を入れ、ようやく金具を見つけ出し、無事にチャイルドシートを取り付けることができました。ホッと一安心です。義母の車で出かける予定は今のところありませんが、万が一娘が急に熱を出したり、体調を崩したときに備えての対策です。
育児休業中のパパが知っておきたい、チャイルドシートの雑学
今回のチャイルドシートの取り付けトラブルを経験して、改めてチャイルドシートの重要性について考えさせられました。ここでは、育児中のパパが知っておきたいチャイルドシートに関する豆知識をいくつかご紹介します。
- チャイルドシートの装着義務 日本では、道路交通法により、6歳未満の乳幼児を乗車させる際には、チャイルドシートの使用が義務付けられています。違反した場合は、違反点数1点が付加されます。
- チャイルドシートのタイプ チャイルドシートは、子どもの年齢や体型に合わせて様々なタイプがあります。
- ベビーシート(乳児用): 生後すぐ~1歳頃まで。後ろ向きで取り付けます。
- チャイルドシート(幼児用): 1歳頃~4歳頃まで。前向きに取り付けます。
- ジュニアシート(学童用): 4歳頃~10歳頃まで。座面を高くし、シートベルトを正しい位置に装着できるように補助します。
- ISOFIXとシートベルト取り付け チャイルドシートの取り付け方法には、大きく分けてISOFIXとシートベルト取り付けの2種類があります。
- ISOFIX: 車に備え付けられた専用の取り付け金具にチャイルドシートを固定する方法です。誤った取り付けが少なく、安全性が高いとされています。
- シートベルト取り付け: 車のシートベルトを使ってチャイルドシートを固定する方法です。車種を選ばずに使用できますが、取り付けが複雑で、誤った取り付けをしてしまうリスクがあります。
- チャイルドシートの正しい取り付け位置 最も安全なチャイルドシートの取り付け位置は、後部座席の中央です。万が一の事故の際に、側面からの衝撃を受けにくいため、最も安全とされています。ただし、後部座席の中央にISOFIXの金具がついていない車も多いので、その場合は助手席の後ろ、または運転席の後ろに取り付けましょう。
育休最終日の夜、そして明日への思い
夕方、妻と娘を義実家に送り届け、一人でアパートに帰ってきました。いつもは、夜になると娘の寝かしつけに苦労しているのですが、今日は一人でゆっくりと過ごす時間があります。
なんだか、忙しさがなくなって張り合いがないな、というのが正直な気持ちです。育児休業中は、朝から晩まで娘中心の生活で、自分の時間はほとんどありませんでした。それでも、娘の笑顔を見るたびに疲れが吹き飛び、育児の楽しさややりがいを感じていました。
育休を取得する前は、育児は女性がするもの、という漠然としたイメージを持っていました。しかし、実際に育児を経験してみて、それは大きな間違いだったと気づかされました。育児は、夫婦二人で協力して行う、共同作業です。
明日からは、また仕事中心の生活に戻ります。これまでのように毎日娘の成長を間近で見守ることは難しくなります。寂しい気持ちもありますが、明日からまた仕事と育児を両立させて、家族を支えていけるよう頑張ろうと思います。
育休期間中に得た、娘との思い出、妻との絆、そして育児の経験は、私にとってかけがえのない宝物です。明日からの仕事も、きっとこれらの経験が活かされるはずです。
最後に、育児に奮闘する全てのパパママに心からのエールを送ります。そして、これから育児休業を取得しようと考えている男性の皆さん、ぜひ育休を取って、かけがえのない時間を過ごしてください。
【コラム】男性育休の現状と未来
私の育休体験を機に、男性育休について少しだけ掘り下げてみたいと思います。
近年、男性の育児参加が叫ばれるようになり、男性育休を取得する人も増えてきました。しかし、日本の男性育休取得率は、まだ世界に比べて低いのが現状です。
2023年に厚生労働省が発表した「雇用均等基本調査」によると、育児休業を取得した男性の割合は、前年の17.13%から上昇し、17.9%でした。しかし、女性の育児休業取得率が80.2%であることを考えると、まだまだ低いと言わざるを得ません。
なぜ男性は育休を取りにくいのか?
その背景には、以下のような要因が考えられます。
- 職場の雰囲気や制度の不備: 育休を取得することに対して、職場の理解が得られなかったり、「男性が育休を取るなんて」という古い慣習が残っていたりする場合があります。また、育休中の代替要員が確保できなかったり、業務が滞ってしまうことを懸念して、育休取得を諦める人もいます。
- 経済的な不安: 育休中は、給料の代わりに育児休業給付金が支給されますが、給料の全額が支給されるわけではありません。そのため、収入が減ることを懸念して育休取得に踏み切れない人も少なくありません。
- 社会的なプレッシャー: 「男は仕事、女は家庭」という固定観念が未だに根強く残っているため、育児は女性がするもの、という無意識のプレッシャーを感じている男性もいます。
男性育休取得のメリット
男性が育休を取得することには、様々なメリットがあります。
- 夫婦の絆が深まる: 育休を夫婦で協力して行うことで、育児の喜びや苦労を分かち合うことができ、夫婦の絆がより一層深まります。
- 子どもの成長を間近で見守れる: 男性が育休を取ることで、子どもの成長を間近で見守ることができ、貴重な時間を共有できます。
- 育児のスキルが身につく: 育休中に育児をすることで、おむつ替えやミルク作り、寝かしつけなど、育児に必要なスキルを身につけることができます。
- 職場でのエンゲージメント向上: 育休を取得することで、仕事と家庭の両立が図りやすくなり、仕事へのモチベーションが向上すると言われています。
男性育休の未来
政府は、男性育休取得を促進するために、様々な施策を進めています。2022年4月からは、**「出生時育児休業(産後パパ育休)」**が創設され、子どもの出生後8週間以内に4週間までの育休を、分割して2回取得できるようになりました。
これにより、男性も柔軟に育休を取得できるようになり、育児参加がさらに進むことが期待されています。
育児は、性別や年齢に関係なく、誰もが経験できる素晴らしいことです。育児を通して得られる喜びや感動は、何物にも代えがたいものです。
私自身、この3ヶ月間の育児休業で、人生観が大きく変わりました。これからも、仕事と育児を両立させながら、娘の成長を温かく見守っていきたいと思います。
明日から、また新しい生活が始まります。このブログで、私の奮闘記を皆さんと共有していけたら嬉しいです。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
#1日後に育休から職場復帰する夫
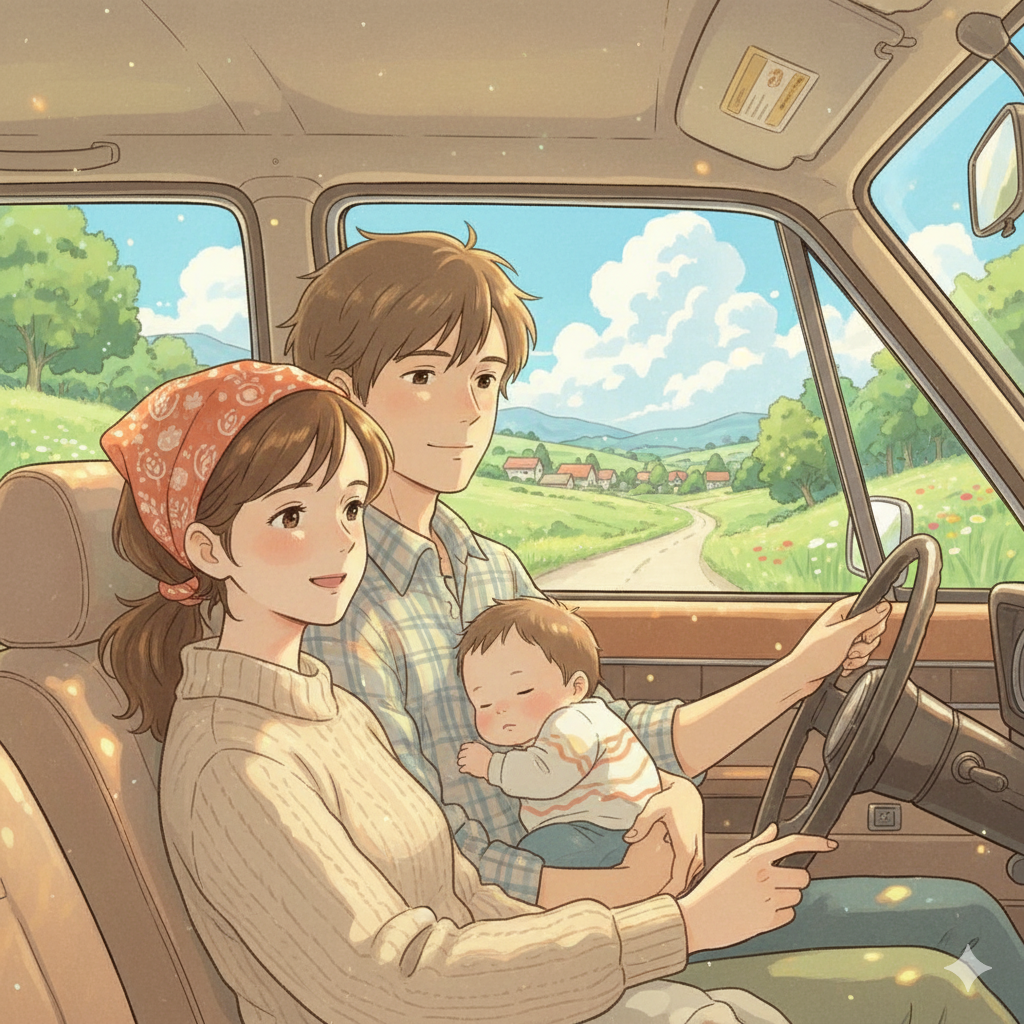


コメント